開放性腎部分切除術を受けられる方へ
H22.6.1〜
腎腫瘍の手術では、通常、腫瘍のある腎臓一個を全て摘出しますが、患者様によっては、腫瘍を含めた腎臓の一部分を摘出する腎部分切除術が行われます。腫瘍を確実に切除しながら、正常な腎臓をできるだけ温存するのが、この手術の目的です。
手術方法
- 全身麻酔で行います。
- 約3〜4時間を要します。(麻酔や手術の準備等で2時間ほどかかります)
- 側腹部の皮膚を15〜20cm切開し、第11肋骨を切除して腎に到達します。(肋骨の処理は、患者様の状態によって異なります)
- 腎の血流を遮断し、氷で腎を冷却し、腎を部分的に切除します。その後、残った腎実質を縫合します。腎切除時に尿路が開放される場合があるので、あらかじめ尿道から腎まで細いチューブを挿入しておき、ここから色素を注入することで、開放された尿路を確認しながら手術を行います。
- 終了時には、出血等を体外に排出するための管(ドレーン)を留置します。
- 術中、出血等の合併症や周囲との癒着・腫瘍の状態などで、腎摘出が必要になる場合があります。
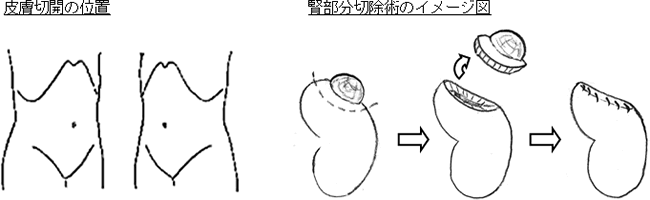
術後経過
点滴、酸素マスク、痛み止めのチューブ、ドレーン、尿を出す管が付いた状態で帰室します。帰室先は、東13階の場合と集中治療室(ICU、東3階病棟)の場合があります。集中治療室の入室は、通常1泊のみです。
術後は、なるべく早期に離床して下さい。手術の翌日〜翌々日から歩行可能です。水分は翌日から、食事は翌日〜翌々日に開始できます。
数日後にドレーンや、痛み止めのチューブを抜き、約1週間で抜糸します。
手術後合併症が無い場合には、8〜10日程度で退院が可能です。(通常、退院の1ヶ月後に外来受診して頂きます。)
合併症(起こりうる望ましくないこと)について
- 腎機能低下:
- 手術後に腎機能が低下する可能性があり、もともと腎機能が不良の場合には、腎不全になる危険性もあります。その際は、点滴や血液透析など適切な方法で対処します。
- 腎出血(腎縫合部からの出血)や、血尿(尿路への出血)を生じた場合には、出血を止めるための適切な処置を行います。血管造影や動脈塞栓術で対応しますが、輸血が必要になる場合や、止血が困難で再手術になる場合があります。
- 尿瘻(にょうろう):
- 修復した尿路から尿が漏れだすことがありますが、尿路にカテーテルを挿入するなど適切に対応します。
- 腹腔内臓器損傷:
- 腎臓の周囲には、腸管、血管、肝臓、胆嚢、脾臓、膵臓などの臓器が密接しています。癒着や病変の広がりなどでこれらの臓器を一部損傷することがあります。その場合には適切な処置を(修復縫合、摘出など)を行います。
- 腸閉塞(イレウス):
- 手術後一時的に腸の動きが悪くなり、経口摂取開始が遅れることがあります。
- 感染:
- 創部やお腹の中に感染が起こり、高熱が出たり、傷が治りにくい場合があります。その際には、抗生物質を使用するなどの治療をします。
- 傷の痛み:
- 側腹部の筋肉を切開するので、ある程度の痛みが生じます。強い時には鎮痛剤等を使用しますのでスタッフにご相談下さい。
- その他:
- 予測し得ないことが起こる可能性もありますが、早急に対応します。また、教育研究の目的で手術の過程を録画・保存することがあります。
- 死亡率:
- この治療による死亡率は0〜0.5%と報告されています。
説明日 年 月 日
説明医師