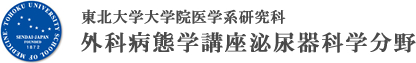代表的疾患:前立腺癌
はじめに
近年、著名人が前立腺癌に罹ってその治療経過を公表したり、また、亡くなったりと言うマスコミの記事を多く目にするようになりました。身近に感じられるようになってきた前立腺癌ですが、これはいったいどの様な病気なのでしょうか?それには、まず前立腺とは何か、そしてそこに出来る癌とはどの様なものかを知る必要があります。
大事なことは2つ、
- 前立腺癌は早く発見する手段がある。
- 前立腺癌には多くの治療手段があり、早期に見つかれば根治できる。
ということです。
前立腺の解剖
前立腺は膀胱と尿道の間にあり、正常では栗の実大で重量は20gほどです。診察は直腸診を行います。肛門より人差し指を挿入すると、指を奥まで入れた状態で前立腺を触れます。触診での固さ、大きさ、痛みの有無などをもとに、前立腺の状態、病気を診断することが出来ます。
その他の前立腺付近の解剖でよく出てくる名前として、精管(精子の通路)、精嚢(精液を貯める袋)、といった精液の通り道と、内尿道口(内尿道括約筋)、前立腺部尿道、膜様部尿道(外尿道括約筋)といった排尿の通り道の名前があります。また前立腺のやや直腸よりの両側には、神経と血管の束が隣接していて、この神経は勃起機能に関与します。前立腺全摘除術時にはこの神経を温存し術後の勃起障害EDを減らす操作が行われます。細い神経ですが、手術時の解剖として重要な部分です。
前立腺の周囲には被膜があり、その内部は辺縁領域、移行領域、中心領域と呼ばれる3つの腺組織と、前部線維筋性間質と呼ばれる非腺組織に分けられます。この解剖は病気の発生部位という点で臨床的に重要で、前立腺肥大症は移行領域に、前立腺癌の多くは辺縁領域に発生します。前立腺の大きさは生涯一定ではありません。思春期になると急速に増大し、20歳代前半で最高に達し20g前後になります。青壮年期はほぼ一定の大きさですが、40歳代後半から多くの人では前立腺肥大が進み徐々に大きくなります。
前立腺の役割
前立腺の働きは精液の一部を作ることです。この精液が精子と一緒になって射精されることにより、前立腺液が精子を外敵から守りつつ、卵子との融合を導く働きをしているようです。
ついでに射精のしくみも簡単に説明します。射精は神経を介して起こる脊髄の反射で、まず下腹神経(自律神経)を介して内尿道口の閉鎖と尿道への精液の放出が起こり、続いて陰部神経(体性神経)を介して尿道周囲および会陰筋群の律動的収縮が起こり、精液が体外へ放出されます。精丘から精液が尿道内に出てくるのですが、射精時には精液が膀胱へ流れないように膀胱頚部が閉鎖されます。
前立腺癌とは
前立腺癌は、泌尿器科領域では最も多い悪性疾患で、近年特に著しく増加しています。最近ではPSA({prostate specific antigen=前立腺特異抗原}の頭文字、ピーエスエーと読む)という優れた腫瘍マーカーの普及もあり、前立腺癌はより早期に発見される様になってきています。治療によって癌が治癒することも期待でき、根治療法として手術療法や放射線療法が行われます。大まかな予後は、前立腺癌が前立腺内に限局している場合(Stage A、B)は5年生存率70-90%、前立腺周囲に拡がっている場合(Stage C)は50~70%、リンパ節転移がある場合(Stage D1)は30~50%、骨などに遠隔転移がある場合(Stage D2)は20~30%です。
前立腺癌が男性癌のトップに!!
前立腺癌の罹患率(10万人あたりで、1年の間に新たに前立腺癌と診断される人の数)を人種毎に見てみると、高い順に①黒人、②白人、③黄色人種となります。アメリカでは、臓器部位別にみると前立腺癌の罹患率の頻度が最も高く、男性癌の約30%が前立腺癌です。米国男性の前立腺癌の生涯罹患リスクは17%で、これは一生の間に6人に一人が前立腺癌にかかる計算になります。日本でも前立腺癌の罹患数は急激に上昇しています。2011年における男性の癌では胃癌に次いで第2位(罹患率は10万人あたり126人)でした。
しかし、2015年の推計では、ついに男性癌のトップになり、年間の新患者数は98,000人と予想されています。日本人男性の前立腺癌の生涯罹患リスクは10%、すなわち一生の間に10人に一人が前立腺癌にかかる、という驚くべき数字です。また2015年の前立腺癌死亡者数は12,000人と予想されており、男性の部位別癌死亡数で第6位になります。この傾向は2016年推計でも変わっていません。このような急激な増加の背景としては、高齢化、食生活の欧米化などの他に、PSA検診など診断方法の進歩が関係しています。
前立腺癌の診断とPSA
前立腺癌を早く見つけるには、何と言ってもPSAの測定が重要です。このPSAは前立腺癌の診断と治療に極めて有用な手段です。これは前立腺癌の“マーカー”、いわば“足跡”とも言うべきものです。採血によってこの値を測定するだけで、受診者に前立腺癌あるか否かの目安をつけることが出来ます。
PSAの正常値は決まっていません。しかし、実際の診断においては4.0 ng/mlを基準値とし、これを上回る場合を癌の疑いありとして精密検査(前立腺生検)をおこなうのが一般的です。これは肛門から超音波の道具を挿入して前立腺を直接観察しながら、細い針を前立腺に直接刺して糸状の組織を採取してくるものです。東北大学泌尿器科では外来日帰り検査で行っていますが、一泊程度の入院で行っている施設もあります。採取した組織は専門の病理医が顕微鏡で検索して癌のあるなしを判定します。通常結果が判明するまで約2~3週間かかります。
PSAが4.0 ng/mlを越えても全員が前立腺癌と診断されるわけではありません。前立腺肥大症、直腸診後、尿路感染症の合併時などでもPSAの上昇が見られるので注意が必要です。一般に、4.0~10.0 ng/mlの群では15~30%に、10.1 ng/ml以上の群では30~80%に癌が検出されます。
PSA検診で前立腺癌死亡率が減少
PSAはたった1mlの採決で前立腺癌の早期診断を可能にします。簡便で有用であるため、前立腺癌のスクリーニング(検診)に広く用いられています。2009年と2010年に相次いでヨーロッパから大規模研究結果が報告され、PSA検診が前立腺癌死亡率を減少させることが証明されました。前立腺癌の好発年齢である50歳になったら年1回のPSA検査をお勧めします。最近では自治体による住民検診、職場検診、人間ドックなどにおける検査項目にオプションとしてPSAも組み入れて測定することが多くなってきました。仙台市では50歳から5歳毎にPSAチェックを勧める方式の節目検診を行っています。自身の生活や仕事状況に合わせた検診システムを利用されると良いでしょう。
前立腺癌の治療
前立腺癌の治療を進めるには、まずGleason score(グリソン スコア)と呼ばれる癌の悪性度と病期(癌の体内での広がり具合)を確定します。Gleason scoreは前立腺生検での癌の診断と同時に診断されます。病期は画像検査で診断します。前立腺内の癌の局在や広がりの診断は主にMRI検査で行います。遠隔転移の診断は骨シンチやCTなどを行います。表1および表2に示したように一般的に病期A~Dに分類する方法とTMN分類とが用いられています。病期A,B,C(T1-4N0M0)を限局性癌、転移のある病期D(N1やM1)を進行癌と呼びます。これらGleason scoreと病期とに加えて、患者自身の年齢、希望、併存症の有無等を総合的に考えて治療方針を決定することになります。
限局性前立腺癌の治療
限局性前立腺癌では、まずリスク分類を行い、そのリスクに対応できる適切な治療法を選択します。詳しくは、検査・手術の説明書「限局性前立腺癌の治療を受けられる方へ」を参照ください。
1)リスク分類
PSA値、癌の悪性度(グリソンスコア)、癌の進展状況(病期)により、治療後の再発の危険度(リスク)を3段階に分け,治療方針決定の目安にします。
【低リスク群】: PSA≦10 、グリソンスコア≦6(3+3)、病期T1a〜c/T2a
*東北大学ではPSA≦10、グリソンスコア 3+4、病期T1a~c/T2aも低リスク群としています。
【中間リスク群】:10<PSA≦20 または グリソンスコア7 または 病期T2b
【高リスク群】: PSA>20 または グリソンスコア≧8 または 病期T2c/T3
2)リスク分類と治療法
【低リスク群の治療】低リスク群では癌は比較的おとなしいことが多いため、治療により再発する可能性は少ないとされています。場合によってはすぐに治療しないで経過を見ることもあります。
- 手術:前立腺全摘術(ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術)で行っています。
- 放射線:強度変調放射線療法(IMRT)/小線源療法から選択します。
- 監視療法(無治療経過観察):経過を見ながら必要があれば根治治療を行います。
【中間リスク群の治療】中間リスク群では低リスク群に比べて癌の悪性度が高くなるため、適切な治療が必要です。
- 手術:前立腺全摘術+骨盤リンパ節郭清(ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術)
- 放射線:半年間のホルモン療法+強度変調放射線療法(IMRT)
小線源療法は一部の中間リスク群(比較的小さな癌)のみが適応になります。
【高リスク群の治療】通常の治療では再発の可能性が高いため、できるだけ根治性を高める方法を併用して治療を行います。
- 手術:前立腺全摘術+骨盤リンパ節郭清(ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術)
- 放射線:半年間のホルモン療法+強度変調放射線療法(IMRT)
小線源療法は高リスク群では適応になりません。
進行癌の治療
進行癌になると癌が前立腺以外にも広がっているため根治は難しく、内分泌療法を行うことになります。前立腺は良性組織であっても癌であっても、男性ホルモンに依存して活動しているという他の癌には殆どみられない際だった性質を有しています。ですから、この男性ホルモンを遮断してやると前立腺癌の細胞はそれが前立腺そのものにあっても転移先の骨にあっても、活動を休止して冬眠状態のようになってしまうのです。これに伴ってPSAも下降してきます。このような、男性ホルモンを遮断する治療法が内分泌療法またはホルモン療法と呼ばれるもので、現在日本でも広く行われています。
実際には男性ホルモンの生産工場である精巣(睾丸)を摘出する、または精巣が男性ホルモンを分泌しなくなるような薬剤を定期的に注射する等の方法がよく用いられます。また、精巣から分泌された男性ホルモンが体内で効果を発現しないようにするための内服薬もあります。このように切れ味のよい内分泌療法ですが最大の問題点は、効果が長続きしないということです。男性ホルモンを遮断し続けても冬眠から目覚めて再び活発に活動しはじめる癌細胞が現れてくるのです(去勢抵抗性前立腺癌)。内分泌療法開始後どれくらいの期間をおいてホルモン抵抗性を獲得してしまうのかはよく分かっていません。早い患者で数ヶ月、長続きする患者だと5~10年くらいといわれています。グリソン スコアの高い人、病期の進んだ人ほど早く抵抗性となります。
去勢抵抗性癌の治療
初期の内分泌療法の効果がなくなった病態を去勢抵抗性前立腺癌(CRPC)と呼びます。進行が比較的緩徐であれば、エンザルタミド(商品名イクスタンジ)やアビラテロン商品名ザイテイガ)などの新規ホルモン療法で治療します。これらの治療でも進行したり、痛みの悪化など急速な進行が見られる場合などは、ドセタキセル(商品名タキソテール)による化学療法が選択されます。ドセタキセルの効果がなくなった場合は、カバジタキセル(商品名ジェブタナ)へ変更します。
その他にステロイド剤、女性ホルモン剤、経口抗癌剤などが使用されることもあります。これら以外にも新しい薬剤も開発されつつあり、東北大学では積極的に臨床治験に取り組んでいます。詳細については主治医にご相談下さい。
最後に
前立腺癌はPSAの採血という簡便な手段のみで癌を発見することが出来、それによって前立腺癌死亡率を確実に減少させることが出来ます。50歳以上の方は是非毎年PSAチェックを受けて下さい。前立腺癌が見つかった場合、十分に納得できる治療を受けることが大切です。東北大学泌尿器科では、患者さんの要望に可能な限り沿った情報と治療を提供しています。